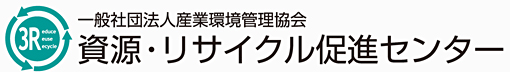環境学習支援
世界のごみ、リサイクル

世界各地のごみ、リサイクル、環境教育などのエコ事情について、現地在住の方にわかりやすくレポートいただき、ご紹介しています。
掲載国:スウェーデン、アメリカ、シンガポール、ドイツ
 スウェーデン
スウェーデン
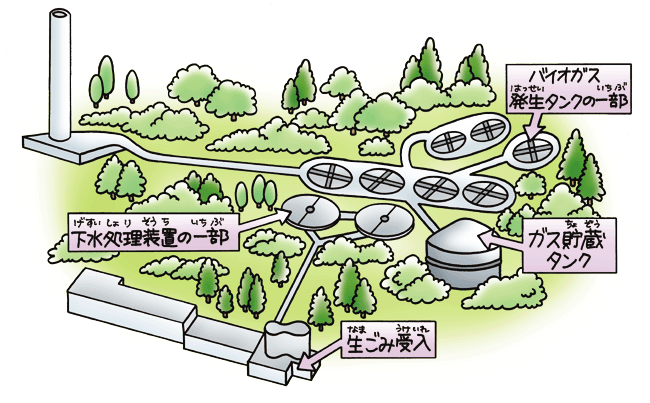
ストックホルム市の持続可能なまちづくり
ストックホルム市には、エコシティ地区があり、ごみのバキューム 収集システムや緑に囲まれた下水処理場とバイオガス生産工場があります。生ごみと下水処理過程で発生する下水汚泥からバイオガスを作り、市バスや家庭の燃料に利用しています。

スウェーデンの環境教育
スウェーデンには、熱心に環境に取り組んでいる学校であることを認める「グリーンフラッグ」という制度があります。全校の学級が取り組むこと、1~2年間の取り組みをレポートにまとめて認証団体に提出すること等でグリーンフラッグの旗を受け取ることができます。
また、スウェーデンにある290の市のうち、環境に熱心な90の市では、就学前から高校までの環境教育をサポートする自然学校があり、学びを支援しています。
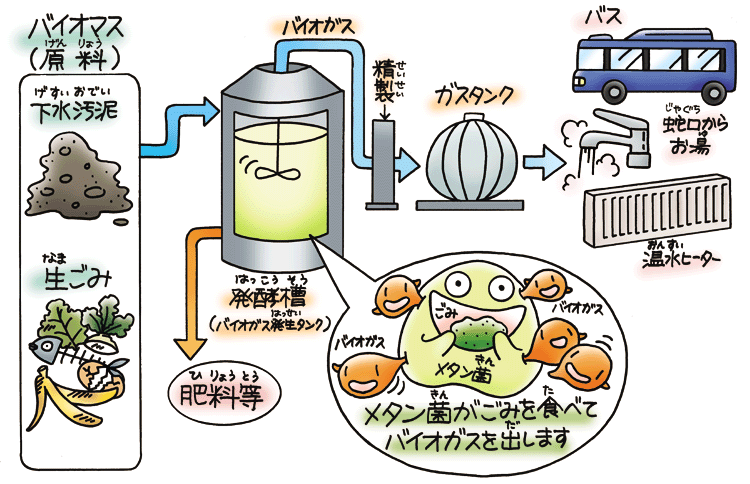
スウェーデンのごみ処理、リサイクル
スウェーデンの家庭・会社・商店から出されるごみは、主に地域のエネルギー源として使用されています。また、原料としても利用されています。
<ごみ処理の内訳(2013年)>
50.3%:焼却後、熱をリサイクル(地域暖房の熱と発電)
33%:リサイクル(原料に戻す)
16%:肥料化、バイオガスの生産
0.7%:埋立て
 アメリカ サンフランシスコ市
アメリカ サンフランシスコ市

サンフランシスコ市の4R
サンフランシスコ市では、 2020年(平成32年)までにゼロウェイストを目指し、4R(Reduce、Reuse、Recycle、Rot)活動を進めています。
水筒の利用が便利(写真1):Reduce
サンフランシスコ市では2014年に、市の所有する建物や広場ではペットボトルの販売が禁止されました。しかし市内では「水筒」に水を入れる場所がデパート、空港、市役所、会社、学校などいたるところにあり、便利です。
ごみが芸術に変身(写真2):Reuse
サンフランシスコ市のトランスファーステーション(さまざまな種類のごみが集められリサイクル資源に仕分けされる作業場)では、アーティストがその中に制作拠点を置き、常に作品づくりに取り組んでいます。
生ごみの分別収集が義務化されている:Recycle、Rot
2009年から生ごみの分別収集が義務化されました。
アメリカで義務化されているのは、サンフランシスコ市だけです。

サンフランシスコ市のごみ処理、リサイクル
サンフランシスコ市では、ごみを全く燃やしません(清掃工場がありません)。ごみの分別は3種類で、種類に応じてごみ箱があります。ごみの収集は週に一度です。
1)青(リサイクル):プラスチック、ガラス、かん、紙
2)緑(コンポスト):生ごみ、紙容器、庭の植物など
3)黒(埋め立て):埋め立てごみ
 シンガポール
シンガポール

シンガポールのごみ問題
シンガポールのごみの量は、1970年の1,260トン/日から2014年には8,338トン/日へと、約6倍に増加しています。このため、東京23区程の、小さな国土でいかにごみ処理するかが大きな問題です。
また、シンガポールでごみをポイ捨てすると最高で1000$(約8万円)の罰金です。
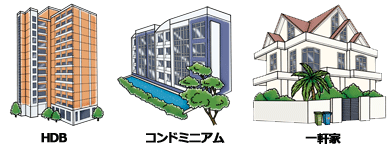
住居の建物の種類で違うごみの出し方
シンガポールでは住居の建物の種類でごみ処理料金やごみ出しの方法が違います。
ごみ処理料金(2015年)
シンガポールではごみ処理料金は有料です。
- HDB:660円/月
- コンドミニアム:管理費に含まれている
- 一軒家:2,190円/月
ごみ出し
ごみは主に「一般ごみ」と「リサイクルごみ」に分別しています。
一般ごみのごみ出しは
- HDB、コンドミニアム:
各家庭または各階のダストシュートにごみ出し、下層のごみ箱に落ちたごみはごみ収集車が箱ごと回収し、清掃工場へ運びます。
最近はシュートから落ちてきたごみを、空気の力で吸い取り、自動的にごみ集積所まで運ぶ(バキュームごみ集収システム(PWCS))システムも挑戦されています。 - 一軒家:
ごみ収集業者が各家の住所を書いた2種類のごみ箱を、各家の前設置し、そこにごみ出しをします。

シンガポールのごみ処理、リサイクル
一般ごみ
燃えるごみは焼却で90%体積を減らし、焼却灰は燃えないごみともに、シンガポール北西部沖合30キロのセマカウ島に埋め立てられます。
セマカウ島の埋め立て地の建設が原因で、島の沿岸のマングローブ林が失われたため、マングローブの苗木が植林されています。
リサイクルごみ
集収されたリサイクルごみは、品目ごとに分けられ、その後それぞれの品目のリサイクル工場へ運ばれ、再生されます。
 ドイツ ハノーファー市
ドイツ ハノーファー市


リサイクリングホフ
リサイクリングホフはごみ回収所のようなところで、市内にいくつかあります。市民は無料で持ち込めますが、企業からのごみは、有料になります。
リサイクリングホフには、ごみの種類別に大きなコンテナーが置いてあり、電池、廃材プラスチックや、枝、紙などを回収しています。

ハノーファー市のごみ処理、リサイクル
ハノーファー市では、市に委託されたハノーファー清掃公社が住民からごみ処理費を集め、ごみ処理しています。集めたごみのうち、びん、古紙、電池や電化製品、薬品などは、専門業者に処理を依頼します。
容器包装(ガラス、紙、プラスチックなど)は、ハノーファー清掃公社がDSD(ドイツデュアルシステム)から依頼を受けて収集し、DSDの処理工場に運びます。そこで分別され、リサイクルされます。商品の入れ物なので、商品を売る人たちの責任で処理することになっています。

デポジット制度/リユース対策の現実と難しさ
ドイツでは一部の飲み物のびんやペットボトルに対し、デポジット制度が導入されています。デポジット制度とは、製品価格に容器代のデポジットを上乗せして販売し、消費者が使用済み容器を返却した際にデポジット分のお金が返却される、使用済み容器の回収を促進する制度です。
ドイツでは、リユースを促進するために、リユース容器のペットボトルには15セント(約20円)、リサイクル容器のペットボトルには25セント(約30円)と、リサイクル容器の方が高いデポジットがかかっています。
その結果、リユース容器の利用は一時的に増えましたが、その後リサイクル容器の利用が増え、今では半分以上がリサイクル容器となっています。

ハノーファー市の環境教育
ハノーファー市では小学校1年生の時から、ごみの分別やリサイクルついて学び、家庭でも分別するように指導されます。
また、幼稚園から高校生を対象として、市営の環境教育施設・学校生物センターがあり、学校での学びを支援しています。